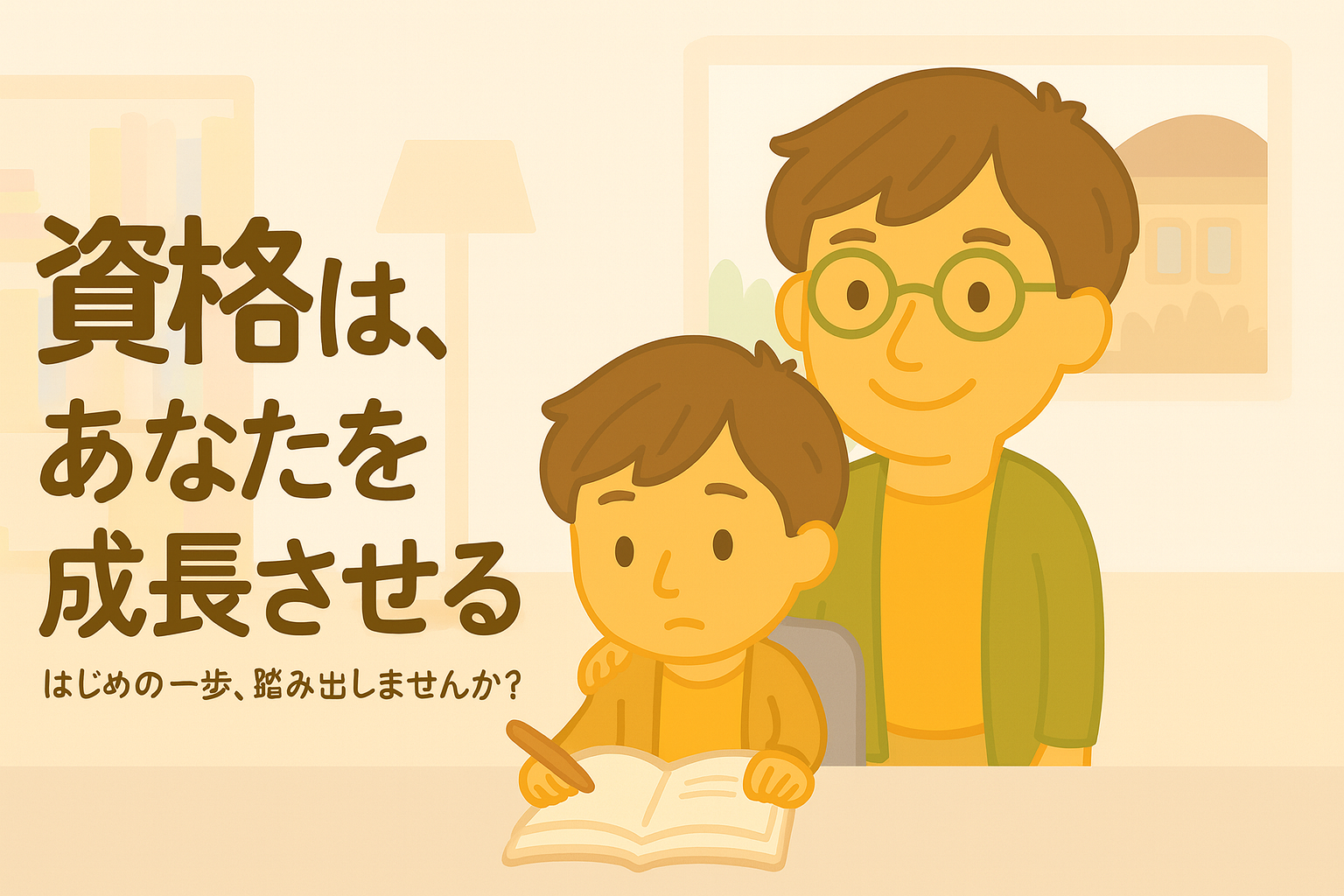いろんな働き方があっていい。昼も夜もみんなのタスキで介護現場は回ってる。みんなの得意を持ち寄って支え合おう。
介護の職場で働いていると、必ず耳にする「夜勤専従」という働き方。
でも実際には、現場の中でもその役割や存在感はちょっと“特殊”に見えるかもしれません。
この記事では、介護業界に20年関わり、今は管理者として現場を見守る私が、夜勤専従という働き方のリアルな印象と、メリット・デメリット、そして向いている人の特徴をお伝えします。
「夜勤専従って気になるけど、実際どうなんだろう…?」
そう思っているあなたに、安心と納得を届けられたらうれしいです。
夜勤専従ってどんな働き方? 管理者としての印象と変化
正直なところ、私は夜勤専従という働き方を、最初は少し距離を置いて見ていました。
「日勤で利用者の生活を把握して、その上で夜間のケアをするのが介護の基本じゃないか」
「夜だけ勤務するスタッフに、利用者さんも安心できるのか?」
そんなふうに感じていたんです。
でも今は、少し見方が変わってきました。
働き方が多様化し、介護現場もチームで支え合う時代に入っています。
“すべてのスタッフが日勤も夜勤もこなす”という形が、必ずしも最適とは限りません。
「夜を支える役割」として夜勤専従がある。
そんなふうに考えられるようになってから、夜勤専従の価値や必要性がよく見えてくるようになりました。
夜勤専従のメリット4選──自由と安定を両立できる働き方
夜勤専従の働き方には、確かにデメリットもあります。
でも、その一方で「これは夜勤専従ならではのメリットだな」と感じることも多くあります。
① 自分の時間を自由に使える
日勤のように毎朝決まった時間に出勤する必要がない分、日中の時間を自分でコントロールできるのは大きな魅力です。
たとえば…
- 明けの日を“自分の休日”として活用できる
- 役所や病院の用事も平日昼に済ませられる
- 子どもの学校行事に参加しやすい
夜勤を経験したことのある方なら、「明けのあの解放感」はなんとなく覚えていませんか?
あの時間の自由さは、夜勤専従だからこそ得られるものかもしれません。
② 人間関係のストレスが少ない
介護の現場は、どうしても人間関係が密になりがちです。
とくに日勤帯はスタッフの数も多く、連携や調整が求められる場面も多いですよね。
その点、夜勤専従は基本的に一人勤務が中心です。
「チームプレイが苦手」「人の目が気になる」という方にとっては、
“自分のペースで働ける”という安心感が大きな魅力になるでしょう。
実際に、こうした理由で夜勤専従を選ぶスタッフも少なくありません。
③ 夜勤手当で収入が安定しやすい
パートや派遣で働く場合でも、夜勤には手当がつくため、時給換算で高めになります。
たとえば…
- 日勤:時給1,200円×8時間=9,600円
- 夜勤:時給1,300円+夜勤手当5,000円×1回=約17,000円
このように、実働回数が少なくても、生活費をカバーできるというメリットがあります。
週2~3回の勤務で、月収25万〜30万円前後を得ている方も珍しくありません。
④ ダブルワークや副業との両立がしやすい
自由な時間を活かして、日中に別の仕事や学びを両立する人も増えています。
たとえば…
- 平日昼はデイサービスのパート勤務
- 副業としてライティングや資格取得の勉強
- 家族の介護や育児との両立
こうした柔軟な働き方ができるのも、夜勤専従の大きな強みと言えるでしょう。
夜勤専従のデメリット──体調・孤独・キャリアの壁とは?
一方で、夜勤専従の働き方には、いくつか注意すべき点もあります。
① 睡眠・体調管理に気を配る必要がある
夜間に働くということは、体内時計が日勤の人とは逆になるということ。
- 寝つきが悪くなる
- 生活リズムが崩れて疲れやすい
- 食生活が不規則になる
こうした問題が続くと、健康を損なうリスクも高まります。
特に長期で夜勤専従を続ける場合は、自己管理の力が必要です。
② 情報共有の遅れや孤立感
日勤帯のスタッフと顔を合わせるのは、朝の引継ぎと夕方の申し送りくらい。
そのため…
- 日中に行われたケアの変更が伝わっていない
- チーム内の動きがわかりづらい
- 自分だけ取り残されたような気持ちになる
こうした“情報の断絶”は、夜勤専従が抱えがちな課題です。
施設側も、引継ぎノートやアプリなどで仕組み的なフォローが必要ですし、
夜勤側も「受け身ではなく、自分から取りに行く姿勢」が求められます。
③ キャリアの積み上げが難しくなりやすい
リーダーや主任といった役職に就くには、日勤帯での経験や関係構築が必要です。
そのため夜勤専従だけでは、どうしてもキャリア評価が難しい面があります。
「今は家庭の都合で夜勤専従だけど、いずれ日勤に戻ってキャリアを積みたい」
そんな方は、定期的にチームとつながる工夫が必要です。
管理者として伝えたい「チームの一員」としての意識
私の施設では、夜勤専従として働いているのは派遣の方や一部のパート職員です。
正社員ではない分、働き方に自由がある一方で、チームとの接点が限られるのが実情です。
だからこそ伝えたいのは──
夜勤専従も“チームの一員”であることを忘れないでほしいということ。
たとえば…
- 情報共有に積極的に参加する(引継ぎノートやアプリへの記録)
- 小さな変化にも気づき、朝にしっかり申し送る
- ケアの変更点や困りごとは遠慮せず報告する
夜勤の視点からの気づきが、利用者の生活を守るカギになることもあります。
昼も夜も、それぞれの時間を守る人がいてこそ、介護の現場は回っています。
夜勤専従の存在は、決して“外部”ではなく、“必要不可欠なピース”です。
夜勤専従から日勤へ──働き方を変えたスタッフのリアル
私が管理者として見てきた中で、夜勤専従から日勤へ戻ったスタッフもいます。
たとえば…
- 日勤帯の人間関係に悩み、一時的に夜勤専従へ
- 家族の事情で夜勤を選んでいたが、子どもの成長とともに日勤へ
- 夜勤手当による収入を優先し、短期的に夜勤へシフト
中には、「夜勤で自信を取り戻して、再び日勤に戻った」という方もいました。
それぞれの選択には、それぞれの事情があります。
大切なのは、どんな働き方でも“積み上げ”として捉えることだと思います。
夜勤専従を選ぼうとしているあなたへ──自由と責任のバランスを
夜勤専従という働き方は、逃げでも妥協でもありません。
むしろ、ライフスタイルに合わせて働き方を選ぶ時代において、
**「自分に合ったキャリアの形」**のひとつだと、私は思っています。
とはいえ、自由には責任も伴います。
- 情報共有を怠らない
- チームの一員としての意識を持つ
- 自分の体調としっかり向き合う
この3つを意識できるなら、夜勤専従という働き方は、あなたにとって大きな味方になります。
まとめ:夜を支える人がいるから、介護の現場は回っている
夜勤専従は、誰かが担わなければ成り立たない、とても大切な役割です。
日勤が苦手でも、人間関係がしんどくても、
それでも「誰かの役に立ちたい」と願うあなたの働き方を、私は応援します。
あなたの働き方は、きっと誰かの暮らしを支えています。
そして、あなた自身の人生も、ちゃんと動かしているはずです。
🔗 関連記事はこちらもどうぞ
📘 あわせて読みたい記事
介護職の“これから”を考えるあなたへ
- 🔹 【2025年版】介護職こそ転職サイトを使うべき理由とおすすめ6選
→ 「人間関係を理由に転職を考えるとき」の最初の一歩を丁寧に解説。 - 🔹 介護派遣ってどう?メリット・デメリットを現場目線で語ります
→ 派遣という働き方を知っておくと、今の職場の“選択肢”が広がります。 - 🔹 介護職の転職、いつがベスト?──現場経験20年の視点で答えます
→ タイミングの見極め方を知ると、焦らず自分に合った転職ができます。
🌿 てるよし式メッセージ
あなたの働き方には、いくつもの選択肢があります。